HOME > PT・下元佳子さん
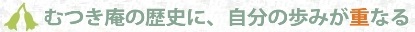

写真:下元佳子さん
むつき庵顧問、一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク代表、社団法人ノーリフト協会理事、理学療法士、介護支援専門員、福祉用具プランナー、生き活きサポートセンターうぇるば高知代表、日本在宅褥瘡創傷ケア推進協会理事。
|
浜田きよ子 下元さんと出会って20年くらいですね。移乗委員会の勉強会で「すごいPTがおられる」と感心していたのです。
下元さん 私はもちろん、浜田さんのことはずっと前から存知上げていたので、「うあ、本物がこんなところにおられる」と興奮していました。近寄っていいのかなと思っていました。
浜田 私がむつき庵を始めて、おむつフィッター研修を始めた時に、排泄ケアのスペシャリストにとって必要なものって、トイレ誘導とか治療だけでなくまさに「排泄しやすい身体」です。そんな身体をどうやって作るのかということを考えた時、下元さんに講習をしていただきたいと思ったのです。
今日、改めていろんな話をすることがとてもうれしく思います。 |
下元さん むつき庵の講師のお話をいただいた時に、私でいいの?と思いました。
でも自分にさせていただいたことを振り返ると、むつき庵の研修の中に入ることは、むつき庵の考え方を吸収していくことが大きいですね。毎回、1時間くらい浜田さんとお茶をしながら話す時間をいただいていますが、それが私にとって大事です。私自身をリセットしたり考え方を変えたりとか。その時間が年に数回あるのが、未熟な私なりに、私の進み方を考える手がかりになっています。技術というもの、それを生かすためにするべきことなどを考えるわけです。人が生きるために関わっていくこととはどういうことか。その芯になるところを浜田さんとのお茶の時間で作っている気がしています。
浜田 私もまさにそうなんです。何のためにこの研修をしているのかと考えると、ケアに関わる人の技術を磨きたいとか、知識を得ていただきたいとか、あれこれ思います。そして良い技術は大切ですが、それをどう伝えるのかということも。何より、その根底にあるもの、人に関わるときに大切なモノとは何か、そして私はこの研修をどうしたいのかなどを、私も下元さんとお茶を飲みながら考え、いろいろなことを考え、方向性を確かめる時間になっています。
 下元さん 私はその時間で得るものがすごく大きいのです。おむつフィッターの同じ2級、1級ですが、自分が気づくと「これは違うんじゃないか」とか視点が変わっているので、伝え方、内容なども。もし、私が講師をお引き受けした初期の自分の話を聞いたら悶絶するんじゃないかと思います。それくらい大きな変化が起きていく時間です。「なちゅは」(一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク)のみんなにも伝えていきたいことだったり。 下元さん 私はその時間で得るものがすごく大きいのです。おむつフィッターの同じ2級、1級ですが、自分が気づくと「これは違うんじゃないか」とか視点が変わっているので、伝え方、内容なども。もし、私が講師をお引き受けした初期の自分の話を聞いたら悶絶するんじゃないかと思います。それくらい大きな変化が起きていく時間です。「なちゅは」(一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク)のみんなにも伝えていきたいことだったり。
おむつフィッター有資格者の方々が、全国20か所にある「なちゅは」に入ってくれたりするのも嬉しいことなんです。それはどういうことかというと、「なちゅは」の行動の中におむつフィッターと共通するものを見出してくれたのだということが嬉しいのです。
浜田 「なちゅは」とおむつフィッターってすごく仲が良いのです。「なちゅは」からおむつフィッター研修に来られたり、あるいはその逆だったり。ものすごく重なり合います。それは、下元さんが考えておられることや私の思うケアの在り方の考えが、その根底に同じ思いを持っていたのだということなのでしょうね。
下元さん 私たち「なちゅは」にとっては、むつき庵の背中を見ながらの行動ですから、同じ思いを感じて参加してくれるおむつフィッターのみなさんがいるということは、間違わずに進めているんじゃないなと、道しるべになっています。
浜田 とても光栄で、こちらこそです。排泄ケアって、暮らし全体に関わるケアです。そしてそこには「姿勢」が大きなテーマになることに気付きました。その専門は理学療法士の方々で、そこを丁寧に伝えていただきたいと願います。その伝え方はセラピストによって様々ですが、下元さんと話していると、「私の技術をどう伝えるか」はもちろん大事だけれど、その高めていく技術の中身が、わかりやすく伝わるとか、やってはいけないことが平易にわかるようになっていたり、そもそも技術って何だろうということを考えていくことにつながっています。
下元さん 嬉しいです。
浜田 受講生の職種や経験、知識は様々です。そのため人によっては、技術を学ぶのは難しいと思います。でも難しいと言ってしまえば技術は伝わりにくくなってしまいます。そこで「これはよくないとか」、「これを外さなければいいとか」、「ケアを受ける人にとってどうなのか」などを、下元さんはちゃんと伝えてくださっていて、ものすごくいいのです。
下元さん 難しい専門性だからあなたには無理でしょうとか、そういうことではなくて、
自分がやっていることの奥底をある程度一般的なこととして使えるようにしていくのが、大事な仕事だと思っています。PT、OTの仲間で話す時には、私たちが介入するということは「その関わった時間に何をするのかではなく、関わっていない時間にこの方がどんなことをされるのか」を組み立てる。そのブランディングができなかったら何の役にも立たない職種なんです。
浜田 そうなんです。たとえば老々介護で夫を妻が介護しているとして、妻がどこまでできるのか、そしてその間の夫はどのように過ごされるのか、また妻や夫にはどのように伝えれば分かるのか、その判断が重要です。
下元さん セラピストは伝えるのが私たちの仕事ですと言って、確かに伝えているかもしれない。でも、自分ができること、理解している形をそのままではなく「相手ができる方法の中で、良い方法」を伝えないと成立しないのです。
浜田 こうでなければならない、と思いこむと、相手には伝わらなかったりするので、現実に落とし込んで、伝わるようにしなければいけません。踏み外してはいけないことと、これだけはやってほしいこと。これはプロがどう伝えるかにかかわっています。そしてそれは実際に使われているのかという評価が必要です。

――浜田さんは、下元さんが実践しておられる「ノーリフト」という言葉についてどう思われていますか。
※ノーリフトは人の手で要介護者を持ち上げるのではなく、リフトなど機器を適切に使って要介護者の負担を減らしていこうとする意識改革、社会運動の側面を持つ介護・看護の概念。
浜田 私たちの普段の暮らしから考えてみると、人に持ち上げられるのも、人を持ち上げるのも、思えば不自然な行為です。
ケアのなかでは、その不自然なことが行われています。そしてそれはケアする人も大変ですが、ケアされる人も、持ち上げられて怖い思いをします。私は施設で二人かかりで持ち上げられる体験をしましたが、すごく怖かったです。そしてその怖さが身体を緊張させます。
その意味でも持ち上げないで介護されることは大事です。それとやさしく触れること。下元さんがおやりになっていることの一つですが「どう触れるか」はすごく大事です。
下元さん ノーリフトをやっているのは、ちょっと乱暴ですが、ノーリフトを広げたいのではなくて、ノーリフトで畑を耕しているつもりなんです。
要するに、どんなにポジショニングを、やさしい触り方を、と言っても、目の前で方法を知らないと、力任せしかできないのです。やさしくポジショニング、やさしくおむつ交換、という研修をやっても起こす時によいしょっとやってしまうのです。それだけで身体が硬くなっていきます。最低限、力任せのケアはやめにしないと。
日本でケアによって結果が出ていない大きな要因が、この力任せの介護にあるんじゃないかと思っています。
畑を耕し芽を出すこと、ひょっとしたら、ノーリフトは耕すではなく栄養なのかもしれません。一生懸命やってきたなかで、一人良くなったとか、なんとなく良くなった感はあっても、すっきりとその成果を見ることができていないということについて、この数十年のジレンマがありました。そこを大きく改善したいのです。力任せのケアはゼロにしたい、それが早いのではと思います。高知県は平成28年にノーリフティング宣言をしたのですが、それで拘縮でカチカチに固まっている利用者さんがいた施設でも、その方もかなり緩んできています。それで排泄が良くなってくるんです。
浜田 確かにそうです!ケアはつながっていますから。
下元さん 拘縮もひどくて自然に便が出ないから下剤をかけておむつをするしかできないと言っていた施設が人の手ではなくリフトで吊り上げてケアしていると、身体が緩んできて、トイレで排便できるようになったので下剤をやめるようになりました。それからその施設では、おむつをはずしたいという次の目標が見えてきました。
その施設では、今までに排泄を学んできた人たちがいて、意識が高いのですが、でも実際にどこから手をつけていいのかわからないと思っていたのですが、そんな人たちが急に活発に動くことができるようになったりとか。おむつフィッター有資格者の方々が知識と技術をノーリフトと組み合わせることで結果を出しやすくしていく、そんな地域を作りたいなあと思っています。
浜田 高知にうかがった時に下元さんに施設を案内していただきました。認知症を抱えた方もトイレに行きたくなったら自分でスタンディングリフトにつかまり、トイレに行かれていましたね。トイレに入っても、ちょうどスタンディングリフトのおかげで姿勢保持しやすく、それがよい排泄につながっています。それを見て、すごいなあと思いました。
それから先ほどの質問ですが、「ノーリフト」という目標をどう考えるのかという問いだったと思うのです。おそらくそれはプロセスであって、目的ではないのです。
よく聞く「おむつゼロ」も、それは結果であって目的ではないのです。それを目標にすると乱暴な解釈も起きやすくなります。紙おむつをパンツ型紙おむつにして、おむつゼロと言っているところもあれば、極力おむつをしないで夜間もトイレに2回誘導するというところもあります。
排泄ケアは個別性が高くて、夜間の排泄はどのようであったらよいかも、人によって異なります。アセスメントのうえでその人にとって何がよいのかを考えるべきところを、こうすると決めることで、考えることから遠ざかっては困ります。
おむつゼロはよい排泄ケアの結果です。それを目標にしてしまうと、ゼロかどうかが焦点になってしまいます。ノーリフトかそうじゃないのか、というそれはまるで流儀の選択のようです。現実は、方法論と目標が混乱しているような気がします。
下元さん 高知も県がノーリフト宣言をしていますが、県も私たちも、考えているのはこれは目標ではなく、双方の快適な暮らしのためにこれをやっていくことが大事なんだということです。そのためには働き方を変えることが大事であり、研修も、実技研修ではなくマネージメント研修をしています。どういう状態にしていくのか、課題があったらどうやって解決していくのかというトレーニングをしています。1年に何回かトレーニングを受けた方々の施設では、2年、3年とたつと変化していきます。ずっと変化し向上していくのは、マネジメントを学んだ人たちの特徴です。
ある施設では、ひとつのユニットで布のパンツとパッドに変え、おむつ(テープ止め紙おむつ)を止めたところ、排泄は変わりました。その法人は特別養護老人ホームや介護老人保健施設など複数の施設があるので、法人全体でそれを採用すると年間2000万円くらい経費削減できることが分かりました。それだけあればおむつではなく、利用者さんに役立つことができるものをそろえることができるので、法人全体で取り組みことになりました。職員さんが何人もおむつフィッター研修に参加されています。
全部つながっています。

浜田 本当にそうです。
食べること、しなやかな体、排泄、それらが全部つながっています。つながっていることが分かればアプローチはいろいろあることもわかります。
いろいろあるけれども、全ての根底にあるのは「身体」です。単に技術の習得ではなく、何のためにするのか、それがぶれてはいけないです。大事なのは、ケアする人の身体をどうやって心地よくしていくか。
私たちはお互いにそこを確認しているんだろうと思います。
 下元さん 私が姿勢管理や動作介助をやっている本当の理由は、身体づくりなんです。究極を言うと。動ける私たちでも運動量が減ると筋量も落ち、限られた姿勢、生活だと制限も起こります。障害を持つとそれはもっと顕著です。筋力は低下し拘縮だらけそんな状態を作っておいて、摂食はどうするとか排泄はどうするとか、そこも考えるけれども、人が生きていく器としての身体をもっと良い状態に変えて、暮らしやすい、健やかに暮らせる身体にしてあげたいのです。どんな介助ならこの人が楽な姿勢になるのかというようなことをやりたいのです。 下元さん 私が姿勢管理や動作介助をやっている本当の理由は、身体づくりなんです。究極を言うと。動ける私たちでも運動量が減ると筋量も落ち、限られた姿勢、生活だと制限も起こります。障害を持つとそれはもっと顕著です。筋力は低下し拘縮だらけそんな状態を作っておいて、摂食はどうするとか排泄はどうするとか、そこも考えるけれども、人が生きていく器としての身体をもっと良い状態に変えて、暮らしやすい、健やかに暮らせる身体にしてあげたいのです。どんな介助ならこの人が楽な姿勢になるのかというようなことをやりたいのです。
10年前はそっちに走りすぎて難しいハンドリングテクニックをとにかく教えて、一人でも良いからそれができる人を増やすというようなことも思っていました。「なちゅは」は、はじめはそんな感じだったんです。介助技術のレベルが高い人を一人でも作ることが、一人でも救い、健やかな体にしていけるんじゃないかと思ったんです。
その人をたくさん作ることは本当に難しいのです。その人たちがやることが、影響力を持つためには、一人だけが高い技術を持っていてもだめです。その人だけが技術水準が高くても、ほかの人がよいしょ、よいしょと持ち上げていたら、私たちが1カ月に1回、1km、2km程度のウォーキングをしたところで何の意味も持たないのと同じで、この人には何の影響もないわけです。認知症の方の周囲に、一人だけやさしい人がいても、ほかの人が大声で怒鳴ったりしていたら当事者はストレスがたまります。それと同じで、最低ラインの、関わる人すべてが「やってはいけないこと」を認識して、それを消していく。それだけでボトムアップでき、現場が変わると思うのです。だから、畑を耕すことができたら、もっとしなやかで健やかな身体づくりができると思うのです。ハンドリング技術の高い人を育てることと、ボトムアップと同時進行でなければは対象者の暮らしは変わらないことに気づきました。
浜田 おむつフィッター研修もそうです。私は、ひどいお尻周りがどれだけ人の身体を損なっているのかをたくさん見てきたので、そこを何とか改善したいと思ってきました。
おむつのことだけではなく、身体のこと、食べること、すべて関係しますが入口をどこにするかです。いったんは困っているおむつを入口にして、だんだん、身体に関心を持ってもらえればと思います。結果的にはそのことは面白く、悪くなかったと思います。
おむつを5枚、6枚重ねて使っていて漏れて困るという現実を抱えていた人たちが研修に来てくれること、これが良かったのです。
下元さん むつき庵が動いてきた年数を振り返ると、社会の排泄ケアって、ものすごく変化しました。
10年前は、6枚、7枚重ねが珍しくなかったです。それを平気で言えた時代です。排泄ケア、お尻周りの良い悪いということが世間に広がっていなかったのです。
その意味では、今は、3枚、4枚はまだあるかもしれませんが、7枚などは本当に期間くなりました。それは確かに底上げされたのだと思います。スペシャリストを作ることも良いのでしょうけれど、それ以上に底上げが大事ですね。
底上げとは「当たり前が変わる」ということですから。
浜田 私は人の暮らしやケアに関心を持ってくれた人が、よりステップアップするということにもこだわってきましたので、下元さんが目指してこられたものとも、むつき庵は重なってきているのだと思います。
お互いに刺激し合っているので、私が「この本が面白かった」と言えば、下元さんはすぐに読んでくださったり。
下元さん 私はずっと浜田さんの背中を見ながらやってきましたので。
人と関わるということはどういうことかをずっと教えてもらっています。
もし私のこの10年が、むつき庵に行かせていただくことがない10年だったらと考えると正直、怖いです。修正もかからずに自分は分かっているのだという思いで走っていたんだろうと思います。それは分かっていないということではなくて、分かっているところが浅かったんだろうと思うのです。恐ろしいなあと思います。
浜田 下元さんの研修を見ると、私がしたかったことってこれなんだと気づくことも多くあります。だから良い刺激をしあっていますね。これからもよろしくお願いします。
下元さん こちらこそよろしくお願いします。
-―Fin.
取材メモ:2018年4月、バリアフリー2018会場に於いて実施。
|